1. 放射無線周波電磁界の概要
多くの電子機器は、テレビ放送局、デジタル無線電話、産業用装置等から何らかの形で電磁放射を受けているが、これにより電子機器の誤作動や機能低下等の影響を引き起こす場合がある。放射無線周波電磁界試験とは、IEC61000-4-3(以下、本規格という)で規格化されているイミュニティ試験であり、電子機器に対して電磁波を照射することで当該機器への影響を評価する試験である。
電磁波は周囲の物体により反射あるいは歪むことがあるため、十分な試験設備が備えられていなければ本規格を満たす試験を行うことは難しく、また試験で照射される電磁波の強度は非常に大きいため、他の電子機器に影響を与えないようにシールドルーム内で行う必要がある。
本稿では、放射無線周波電磁界イミュニティ試験で使用される設備、試験方法等の概要を紹介する。
2. 放射無線周波電磁界試験で扱う電磁放射のレベル
試験でEUT(Equipment Under Test:供試装置)に照射する電磁波の強度、周波数帯等は、製品規格やEUTが最終製品として利用される電磁環境に従って決定される。
本規格では、一般的な試験レベルとして以下の4つのクラスが規定されている。
- クラス1:
低レベルの電磁放射環境。テレビやラジオの放送局が1km以上離れてある場合や低出力送受信機があることを想定したレベルである。 - クラス2:
中位の電磁放射環境。低出力携帯形トランシーバ(定格1W以下)の使用を想定しているが、装置の近くでの使用には制限がある。典型的な商用環境である。 - クラス3:
厳しい電磁放射環境。携帯形トランシーバ(定格2W以上)を比較的近く(1m以上離れて)で使用する場合やISM装置(工業、科学、医療分野で使用される無線周波装置)等が近くにあることを想定した典型的な工業環境である。 - クラス4:
携帯形トランシーバを1m未満で使用する場合や重大な障害を与える他の無線発生源が1m未満にあることを想定したレベルである。 - クラスX:
製品規格、製造業者の社内規格等による任意のレベルである。
試験の際に各クラスで放射する電界強度を表1に示す。
| 試験レベル (クラス) |
試験電界強度 V/m |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 10 |
| 4 | 30 |
| X | 特殊 |
試験周波数は80MHz以上の周波数で行う。80MHz以下の低周波数帯における電磁妨害については、ケーブルを伝わって作用する伝導妨害が支配的になると考えられており、別規格(IEC-61000-4-6 伝導妨害に対するイミュニティ)により試験方法が規定されている。
3. 放射無線周波電磁界試験の特徴
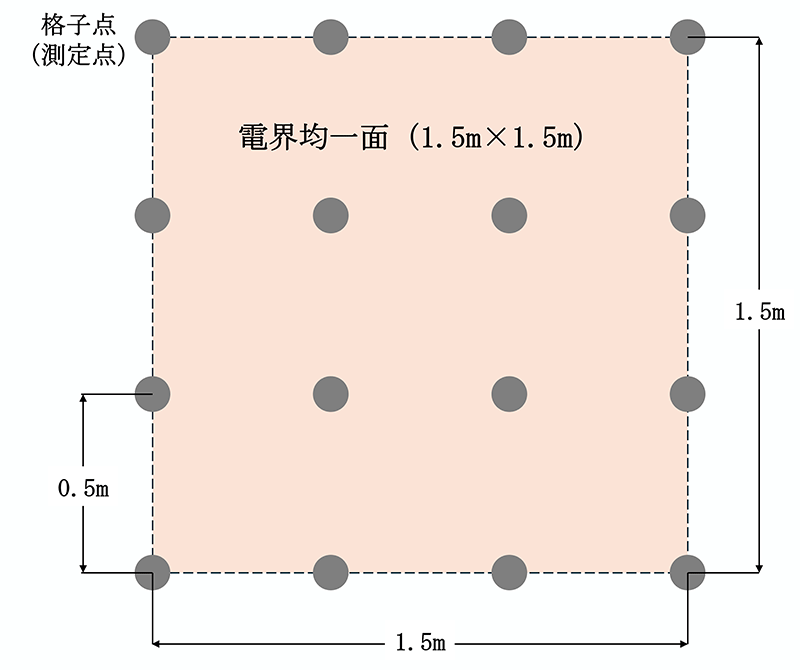
本試験では、EUT全体に対して均一に電磁放射し適正なイミュニティの評価が行えるように、EUTの周囲の電磁界が規定のレベルの範囲内であるかどうかを事前に検証する必要がある。
この検証には、UFA(Uniform Field Area:均一領域)という概念が用いられている。UFAは電界の仮想垂直面であり、一般的に電界均一面と呼ばれている。電界均一面の下端の高さは0.8m、大きさは1.5m×1.5mとするが、EUT全体に対して十分に照射される場合は0.5m×0.5mまで狭めてもよい。ただし、1GHz以上の周波数では、電界均一面内にEUTが収まらない場合においても、電界均一面を0.5m×0.5mとして、複数回に分けてEUT全体に照射する独立ウィンドウ法を適用してよい。
電界均一面は図1のとおり0.5m間隔の格子に分割し、全ての格子点で測定を行う。1.5m×1.5mの電界均一面の場合、測定は32箇所(水平偏波16箇所、垂直偏波16箇所)となる。各周波数において、全ての測定点の75%以上の点で、電界強度が公称値の0dB~+6dBの範囲内にある場合、電界は均一とみなすことができる。なお、電界均一性の検証は年に1回、かつ室内構成を変更(電波吸収体の移動、装置の更新等)した際も行うことが推奨されている。
3-1.測定の手順
測定の手順を紹介する。初めに、図2のように電波吸収体、電界プローブ(電界強度測定用)、電磁界発生アンテナを設置する。電界プローブは電界均一面の測定点の1つに合わせるよう、高さ、横方向を調整する。電磁界発生アンテナは電界プローブから3m離した位置に設置することが推奨されているが、アンプの老朽化等により規定の電界強度が得られない等の理由で、1mを限度に近づけることはできる。ただし、距離が近くなるほど電界均一性の確保が難しくなるため、電界均一面の大きさを小さくする必要性がある。電磁界発生アンテナの向きは水平及び垂直偏波の測定のため都度変更する。これらのセットアップを行った後、基準点(電界均一面内の中心付近でよい)の電界強度と進行波電力を測定する。電磁界発生アンテナには試験レベルの1.8倍の電界強度(10 V/mで本試験を行う場合は18 V/mで均一性を確認)となるよう無変調信号を供給し、周波数のステップは1%とする。基準点を測定した後、電界プローブの位置を1点目に変更し、基準点と同様の測定を行う。この測定を16点目まで繰り返し行う。電界均一性の良否判定については、測定結果から制御用ソフトウェアにより自動で行うことができる。制御用ソフトウェアや測定機器の仕様により測定時間は異なるが、1回の電界均一性の検証でおおよそ1~2日間程の時間を要する。

4. 放射無線周波電磁界試験の手順
試験の際は、前述の電界均一面測定時と極力近いセットアップにした状態で、EUTの側面を電界均一面と一致するように設置する。なお、EUTは最終製品としての利用に近い状態で配置し、付属ケーブルの接続はEUTの製造企業が作成する取扱説明書に従って行う。また、電界均一面測定では、奥行における電磁界の均一性までは検証されていないため、EUTの全ての側面に対して水平及び垂直偏波を照射する。EUTが正常に動作していること、室内に誰もいないことを確認した後、試験を開始する。試験システムの構成を図3、試験の様子を図4に示す。
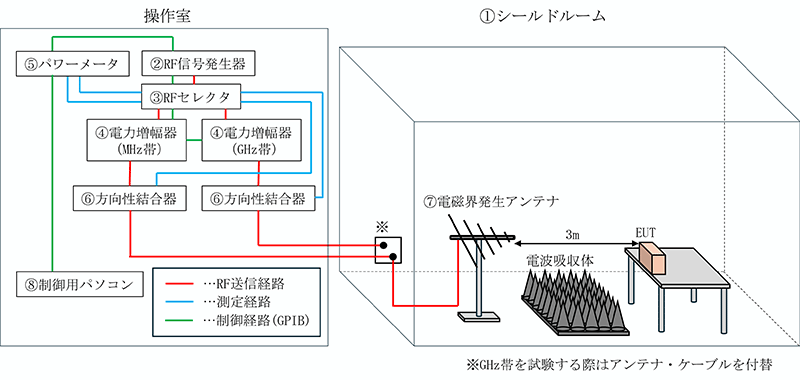
各々の設備の役割は以下のとおりである。
① シールドルーム(電波無響室)
電磁放射の室外への漏洩や外部からの不要な電磁波の侵入を防止するための金属で覆われた部屋。大きさはEUTに対して十分に広い電界均一面が得られるものとし、電界均一性の確保を目的に床や壁面に電波吸収体を追加してよい。
② RF信号発生器
本規格で用いる搬送波信号(1kHzの正弦波、80%AM変調)を発生する。
③ RFセレクタ
②で発生した信号の送信経路を切り替える。
④ アンプ(電力増幅器)
②で発生した信号を規定の電界強度となるように増幅する。MHz帯(80MHz以上1GHz未満)、GHz帯(1GHz以上)それぞれ1台ずつ設置されることが多い。
⑤ パワーメータ(電力計)
④で増幅した信号の進行波電力及び反射波電力を計測する。進行波電力を増減させることで規定の電界強度になるよう調整し、反射波電力はRF送信経路上の異常判別に用いられる。
⑥ 方向性結合器
送信経路上の進行波電力及び反射波電力の一部を取り出し、⑤に送る。
⑦ 電磁界発生アンテナ
④で増幅した信号を空間に電磁放射し、EUTに照射する。要求される周波数帯を満たしたアンテナ(ログペリオディックアンテナ、スタックドログペリオディックアンテナ等)が用いられる。
⑧ 制御用パソコン
各機器を制御し、測定データの保存や自動測定等を行う。
試験中におけるEUTの動作状況の確認は、監視カメラの映像等で確認する。前述の電界均一面測定で使用した電界プローブは、EUTの近くに設置して試験中の電界強度を監視することがあるが、事前に電界均一性は検証されていることから設置しなくてよい。試験結果については、製品規格、製造業者の社内規格等により良否判定する。

5. 放射無線周波電磁界に関連する公設試験研究機関が保有する設備の利用について
国又は地方公共団体が設置する公設試験研究機関では、様々な試験分析機器を保有し、製品開発等を行う企業はこれらの設備を低価格で利用することができる。宮崎県工業技術センターにおいても本稿で紹介した放射無線周波電磁界イミュニティ試験を行う試験機器を整備している。また、当該試験の他にも伝導妨害に対するイミュニティ(IEC-61000-4-6)等の各種EMC規格に沿った試験を行うことができる。電磁妨害対策に当たっては、トライ&エラーを繰り返し行いEMCに適合させていく必要があるが、これらの設備を有効的に活用して製品開発等に役立ててもらいたい。
※ 参考資料
- IEC61000-4-3:2020 電磁両立性-第4-3部 試験及び測定技術 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
- IEC61000-4-6:2023 電磁両立性-第4-6部 試験及び測定技術 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
【著 宮崎県工業技術センター】


