1. 無線機器試験とは
無線技術は、電波を使用して情報を送受信する技術であり、現代社会のさまざまな場面で利用されています。例えば、スマートフォンでの通話やインターネット接続、GPSを使った位置情報の取得、さらにはIoTデバイスによる家電制御など、私たちの日常生活に欠かせない存在です。これらの技術は効率的な通信を可能にするだけでなく、新しいサービスや製品の開発を促進しています。一方で、無線技術の利用が広がる中、適切な動作や安全性を確保するための試験が重要な役割を果たします。
無線機器に関する規制要件は、国によって異なります。メーカーや輸入業者が無線機器を市場に投入する場合、その国ごとの規制要件を満たし、無線機器試験を実施し、認証を取得しなければなりません。無線機器試験および認証は、その国の規制要件を満たしていることを証明するために必要なステップです。
さらに、IoT機器をはじめとする無線機器に対する各国の規制は年々厳しくなっています。最新の情報を収集しながら、無線機器試験をはじめ、自社で取るべきアクションを的確に見極めていくことが重要です。
2. 無線機器とは
まずは、無線機器の定義について簡単に触れておきます。
無線機器とは、電波を使用してデータや音声を送受信するためのデバイスを指します。これらの機器は、通信を効率的に行うだけでなく、さまざまな用途や環境に適応するように設計されています。以下に、代表的な無線機器の種類とその特徴を挙げます。
- スマートフォン: スマートフォンは、多機能な通信機器として知られ、Wi-Fi、Bluetooth、LTE、5Gなど複数の無線通信技術を搭載しています。これにより、音声通話やデータ通信、位置情報サービスなどを利用することが可能です。
- WiFiルーター: WiFiルーターは、インターネット接続を無線で提供するデバイスです。家庭やオフィスで使用されることが一般的で、複数のデバイスが同時にネットワークを共有することを可能にします。
- Bluetooth: Bluetoothを利用したデバイスには、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、マウス、キーボードなどが含まれます。短距離通信に適しており、低消費電力での接続が特徴です。
- ロング・ターム・エボリューション(LTE): LTEは、4G通信規格で、高速なデータ通信が可能です。動画ストリーミングやオンラインゲームなど、大容量データを効率的に送受信できる点が特徴です。
- 第5世代移動通信システム 新無線規格(5G NR): 5G NRは、次世代通信規格として、高速・大容量通信、低遅延、同時多数接続を特徴とします。自動車の自動運転、スマートシティ、AR/VRなどの新たな応用分野を支える基盤として注目されています。
- 全地球測位システム(GPS): GPSは、衛星信号を受信して位置情報を提供する無線機器です。カーナビやスマートフォン、ドローンなど、幅広い用途で使用されています。
- 近距離無線通信(NFC): NFCは、数センチメートル以内の近距離でデータをやり取りする技術です。電子マネーや交通系ICカード、スマートフォンによる決済などに利用されています。
- 無線周波数識別(RFID): RFIDは、電波を利用して物品の識別や追跡を行う技術です。タグとリーダーを組み合わせることで、物流や在庫管理、電子決済などさまざまな分野で活用されています。
このうちBluetoothやWiFiなどの短距離通信技術が搭載されたスマート家電、リモコン、ウェアラブルデバイスなどは、短距離デバイス(SRD)として分類されます。短距離デバイスの特徴は、通信距離が10メートルから最大100メートルと限られているものの、その範囲内で安定した接続を実現しています。ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチ、家電やスマートホーム機器などは、一度ペアリングすれば自動的に接続され、複数の無線機器と常に接続しながら、シームレスに通信ができます。これらのデバイスは、手軽さと多機能性で快適さを提供し、生活に自然に溶け込むだけでなく、技術の進化とともに、さらに便利で豊かな未来を支える重要な役割を担っています。
また、スマートフォン、パソコン、自動運転車、無線を搭載した医療機器などは、短距離デバイスを含め、LTE等の複数の通信規格のモジュールが搭載されている場合、全ての通信規格が認証対象となります。
したがって、一口に無線機器といっても、使用されている通信技術や通信システムは多種多様です。無線機器に関する規制要件が国により異なることは冒頭で述べた通りですが、無線機器の分類によって要件が異なることも、押さえておきたい重要なポイントです。
3. 無線機器試験の概要
本題の無線機器試験について確認していきましょう。
無線試験は、無線機器がその国の法令や技術基準に適合しているかを確認するために行われる重要なプロセスです。私たちの身の回りには、スマートフォンやWi-Fiルーター、Bluetoothデバイスなど、多くの無線機器が存在しています。これらの機器は電波を利用して通信を行うため、技術的な性能や法的な要件を満たしていなければ、他の機器や通信システムに悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、無線試験は安全性や通信の品質を確保するために欠かせないステップです。
以下に主要な国や地域の規格について説明します。
- 日本: 日本では「電波法」に基づき、技術基準適合証明等制度があり、総務省令に定める特定無線設備について、総務大臣の登録を受けた証明機関が技術基準を満たしているかを確認します。
- 北米: 北米ではFCC(Federal Communications Commission)が無線機器の試験規格を策定しています。FCCパート15など、用途や周波数帯に応じた規則があり、適合性を確認するための試験が必要です。
- ヨーロッパ: 欧州連合(EU)では、CEマーキングが求められます。無線機器指令(Radio Equipment Directive, RED)が適用され、EN規格(欧州規格)に基づいた試験が必要です。
- 中国: 中国ではCCC(China Compulsory Certification)やSRRC(State Radio Regulation Committee)が規格を管理しています。特にSRRCは無線周波数の使用に関する試験を行っています。
- 韓国: 韓国ではKC認証(Korea Certification Mark)が必要です。RRA(National Radio Research Agency)が規制を監督し、無線通信機器の安全性や電波干渉を確認する試験を行っています。
次表では、18の国と地域において、無線機器に対してどのような認証が必要とされているかを示しています:
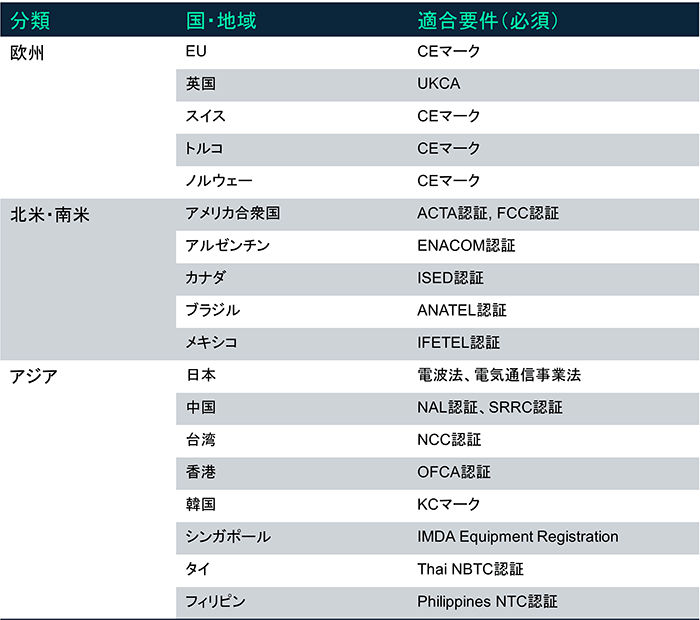
4. 無線機器試験の必要性
ここで改めて無線機器試験の必要性についてまとめます:
- 法令の遵守: 無線機器が各国の法的な基準に適合していることを確認するため。適合していない場合、高額な罰金を科せられるなど、コンプライアンス違反のリスクがあります。なお国や機器の分類により規制は異なることに留意してください。
- 安全性の保証: 無線機器が他の機器や人体に悪影響を与えないことを保証するため。特に医療機器、自動車、航空などの分野では、より高いレベルの安全性が求められます。
- 市場へのアクセス: 各国の基準を満たすことで、初めてその無線機器が上市できます。製品の品質と信頼性を高め、グローバルな市場への展開が期待できます。
無線機器試験が、法令の遵守、安全性の保証、そして市場へのアクセスの基盤となり、必要な認証の取得につながります。また、無線機器の試験に初めて携わる方は、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
- 技術基準を理解する: 対象国や地域ごとの無線規制を確認し、それに基づいて製品設計を行いましょう。
- 試験機関の選定: 信頼性の高い試験機関を選ぶことが、スムーズな認証取得への第一歩です。
- プロセスを把握する: 試験手順や必要な書類を事前に理解しておくことで、無駄な手戻りを防げます。
5. 無線機器試験の流れ
無線機器試験の大まかな流れは以下の通りです(ここでは電波法認証を例にしています)。
- 試験の計画: どの試験規格・項目を実施するかを決定し、必要な機材や条件を準備します。
- 申請書類の準備: 申請書や必要な技術情報を準備します。製品の仕様書や技術図面などが含まれます。
- 試験の実施: サンプルを事前に準備し、該当機器の無線機器試験を実施します。
- 試験結果の評価: 得られたデータを基に、試験基準を満たしているかを判断します。不適合の場合は、設計の修正が求められることがあります
- 審査: 技術基準に適合しているかを確認します。
- 証明書の発行: 適合している場合、証明書が発行され、市場での販売が可能となります。
- 手数料の支払い: 電波法認証を取得する場合、申請手数料が必要です。
6. 無線機器試験の項目・種類
無線機器試験には、以下のような項目があります(ここでは電波法認証を例にし、特性試験の項目の一部を挙げています)。
- 振動試験: 携帯電話など移動や振動が想定される無線機器に適用されます。振動試験後、周波数の偏差を測定します。
- 温湿度試験: 無線機器仕様の最低/最高範囲の温湿度で、無線機器を恒温槽内に放置後、周波数の偏差を測定します。一定の条件を満たせば温湿度試験を省略することができます。
- 周波数の偏差: 規定された周波数帯域内で正しく動作しているかを確認します。
- 占有周波数帯幅: 全電力の99%が含まれる帯域幅で、不要に帯域幅が広がり隣のチャネルに妨害を与えないか確認します。
- スプリアス発射又は不要発射の強度: 使用している周波数以外に不要な電波が発射していないかを確認します。
- 空中線電力の偏差: 無線機器から出力される最大出力電力が規定された範囲内であるかを確認します。
- 隣接チャネル漏洩電力: 割り当てられた周波数帯域の平均電力に対する隣接するチャネルの平均電力比を確認します。
- 副次的に発する電波等の限度: 受信状態で不要な高周波信号を発射していないかを確認します。
7. 無線機器試験の費用
無線機器試験の費用は、試験内容や試験機関によって異なります。一般的には以下のような費用がかかります(ここでは電波法認証を例にしています)。
- 技術基準適合証明手数料: 証明手数料、特性試験ごとに設定された手数料、証明ラベル費用が含まれます。
- 特定無線設備の工事設計についての認証手数料: 新規申込、変更申込により異なります。
- 証明、認証ラベルの料金: 申込台数分の証明ラベルを購入します。
- の他の料金: 証明書や認証書の再発行手数料、試験データ等のコピー、特性試験に係る追加料金など。
料金体系は、試験の内容や試験機関によって異なります。詳しくは各試験機関にお問い合わせください。
8. トレンドワード: 欧州RE指令
最後に、無線機器に関するトレンドワードとして押さえておきたい「欧州RE指令」(無線機器指令(指令2014/53/EU、Radio Equipment Directive/RED)について簡単にご紹介します。
RE指令はR&TTE指令から置き換わる指令として2017年6月より強制移行となりました。無線通信および電波の伝搬特性に基づく、無線測位あるいはそれらのパラメータに関連する情報の取得の目的で電波を意図的に放射および受信する電気/電子製品に適用されます。
- 無線通信: 電波による電気通信であり、電波とは人工的なガイド無しに空間を伝搬する3000GHz以下の周波数の電磁波のこと。
- 無線測位: 対象物の位置や速度、特性を決めることであり、電波伝搬により、これらパラメータにする情報を取得すること。
- 無線機器: 無線通信および無線測位の目的で意図的に電波を放射または受信する電気電子製品またはアンテナ(空中線)、アクセサリーを伴うもの。
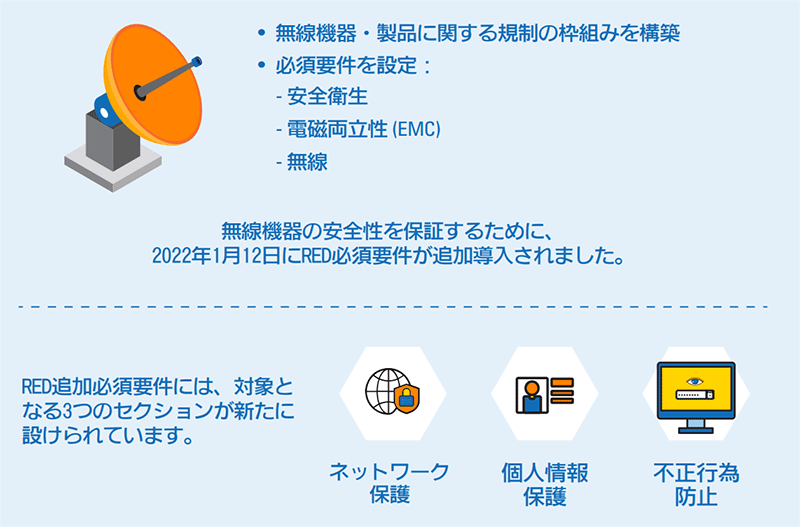
また、近年増加するセキュリティ被害を受けて、欧州では2022年1月に欧州RE指令を補足する委任規制が発表され、新たにサイバーセキュリティ要件が追加されました。これに伴い、2025年8月1日以降に欧州で販売される無線搭載機器の多くは、同指令への適合が義務付けられます。欧州RE指令に適合するためには、適合性評価と型式認証を取得する必要があります。
欧州向けに無線機器を上市している、あるいはこれから上市を検討されている方は、引き続き注視すべきトピックの一つです。
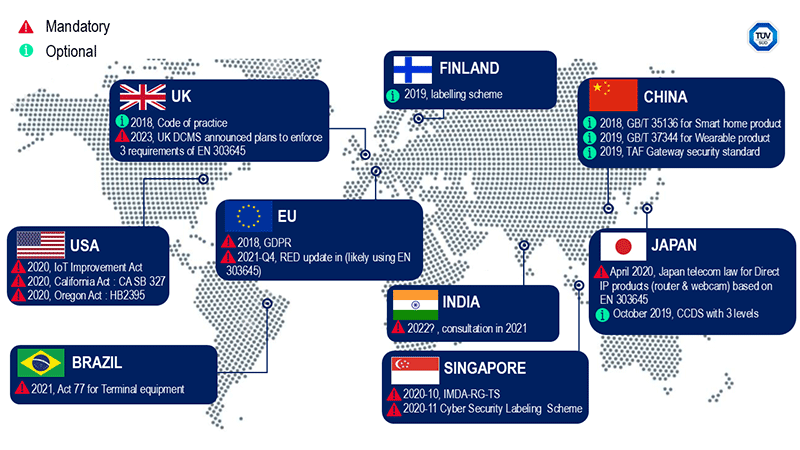
9. おわりに
無線機器は、その手軽さと多機能性によって私たちの生活に快適さをもたらし、自然に溶け込む存在となっています。また、技術の進化とともに、その利便性はさらに向上し、豊かな未来を支える重要な役割を担っています。近年では、複数の通信規格を持つデバイスが家庭で広く普及しており、その結果、規制要件が複雑化し、認証までに要する期間が長くなる傾向があります。こうした背景を踏まえ、各国の規制や技術基準を理解し、適切な試験が実施できる専門的な知見を持つ試験機関や認証機関の協力を得ながら、長期的な視野を持って無線機器の開発や試験に取り組むことが重要です。
 (著)テュフズードジャパン株式会社
(著)テュフズードジャパン株式会社


