1.車載機器・自動車のEMC試験における、製品別の適用ノイズ規格の構成一覧
車載EMC試験は車両(自動車)または車両に搭載される機器に対するEMC試験を意図したものを指し、車載機器・自動車のEMC試験方法を規定したノイズの国際規格には以下のようなものがあるので一覧形式で記載する。
| No. | 規格番号 | EMI/EMS | 規格タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | CISPR12 | EMI | 車両,小型船舶及び内燃機関-無線妨害特性-非車載型受信機の保護の限度値及び測定方法 |
| 2 | CISPR25 | EMI | 車両、小型船舶及び内燃機関-無線妨害特性―搭載受信機のほごのための限度値及び測定方法 |
| 3 | ISO11452-1 | 総則 | 一般原則及び用語 |
| 4 | ISO11452-2 | EMS | 吸収材に裏打ちされたシールドルーム |
| 5 | ISO11452-3 | EMS | トランスバース電磁モード(TEM)セル |
| 6 | ISO11452-4 | EMS | ハーネス励磁法 |
| 7 | ISO11452-5 | EMS | ストリップライン |
| 8 | ISO11452-7 | EMS | 無線周波(RF)電源の直接注入 |
| 9 | ISO11452-8 | EMS | 磁界に対するイミュニティ |
| 10 | ISO11452-9 | EMS | 可搬型送信機 |
| 11 | ISO11452-10 | EMS | 拡張オーディオ周波数範囲における伝導妨害へのイミュニティ |
| 12 | ISO11452-11 | EMS | 残響室 |
| 13 | ISO7637-1 | 総則 | 定義及び一般的考察 |
| 14 | ISO7637-2 | EMI/EMS | 電源線だけに沿う過渡電気伝導 |
| 15 | ISO7637-3 | EMS | 電源線以外の線を経由する容量性及び誘導性結合による過渡電気伝導 |
これらの車載機器におけるEMC試験方法を引用した規格としてEN/ISO13766、EN/ISO14982、IEC61851、EN50498などがありこれらの規格により許容値、周波数範囲、試験レベルなどの試験条件が規定される。
また、上記とは別に車載機器に対する認証制度として一般的にEマーク認証* と呼ばれるものがありこちらも許容値、周波数範囲、試験レベルなどの試験条件が規定されている。
今回はこの認証制度を説明しながら車載機器のEMC試験方法・ノイズ対策について解説する。
1) Eマーク認証制度
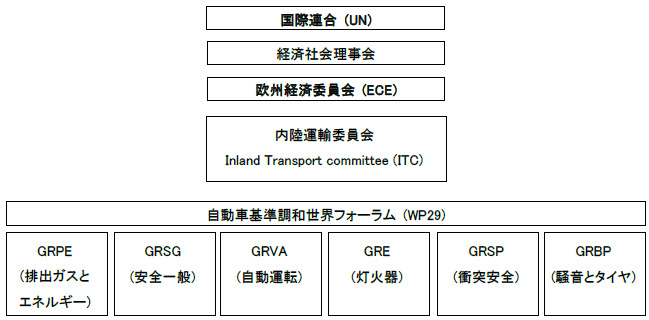
Eマーク認証とはUNECE(国際連合欧州経済委員会)により制定された認証制度であり、「国毎に異なっている自動車基準を国際的に調和」、「認証を輸出入国あるいは地域間でお互いに認め合う相互承認の導入」を目的として1958年に締結された相互承認制度を指す。
Eマーク認証は正式には「車両ならびに車両への取り付け又は車両における使用が可能な装置及び部品にかかる調和された技術上の国連規則の採択並びにこれらの国連規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」という名称の協定であり、1958年当時は欧州域内の国のみの協定であった。
ただ、その後の市場要求により欧州域外であっても国際連合加盟国であれば参加できるようになり現在は欧州域外の国も複数参加している。また、日本も1998年に欧州域外の国としては初となる加盟国として参加している。
また、上述の「国毎に異なっている自動車基準を国際的に調和」、「認証を輸出入国あるいは地域間でお互いに認め合う相互承認の導入」は簡単にいえば、自動車基準の調和 + MRAを指しており1958年協定の加盟国間でMRAを利用して輸出できることを指す。
2) Eマーク認証の要求事項一覧
Eマーク認証を取得する際に必要な要件について規則という形で発行している。
規則は製品、要求内容などで分類されており規則 1~147まで存在している。
規則及びタイトルについて下記に記載する。
規則の名称としてはECE Regulation XX.○○という表記で表現される。
[XXには下記のNo.が入る。○○には規則の版数が記載される。]
例. 規則No.10の第6版である場合、ECE Regulation10.06という表記となる。
(2019年12月時点)規則を下記に一覧で記載する。
| No. | 規則名 | No. | 規則名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前照灯 | 27 | 三角警告板 |
| 2 | 前照灯 | 28 | 警音装置 |
| 3 | 反射装置 | 29 | 商用車運転席乗員の保護 |
| 4 | 後部番号灯 | 30 | タイヤ(乗用車) |
| 5 | シールドビーム前照灯 | 31 | ハロゲンシールドビーム前照灯 |
| 6 | 方向指示器 | 32 | 後部衝突における車両挙動 |
| 7 | フロントおよびリアポジション(サイド)ランプ、ストップランプ およびエンドアウトラインマーカーランプ | 33 | 前部衝突における車両挙動 |
| 8 | ハロゲン前照灯(H1,H2,H3,HB3,HB4,H7,H8,H9,HIR1,HIR2 および/またはH11) | 34 | 車両火災の防止 |
| 9 | 騒音(三輪車) | 35 | フットコントロール類の配列 |
| 10 | 電磁両立性に関する統一規定 | 36 | バスの構造 |
| 11 | ドアラッチ・ヒンジ | 37 | フィラメントランプ |
| 12 | ステアリング機構 | 38 | リヤフォグランプ |
| 13 | ブレーキ(カテゴリM、N、O車両) | 39 | スピードメーター |
| 13-H | ブレーキ(M1) | 40 | 排出ガス規制(二輪車) |
| 14 | 安全ベルト(シートベルト)アンカレッジ | 41 | 騒音(二輪車) |
| 15 | 排出ガス規制 | 42 | バンパー |
| 16 | 安全ベルト(シートベルト) | 43 | 安全ガラス材料の認証に関する統一規定 |
| 17 | シート | 44 | 幼児拘束装置 |
| 18 | 不正使用防止装置 | 45 | ヘッドランプ・クリーナ |
| 19 | 前部フォグランプ | 46 | 後写鏡 |
| 20 | ハロゲン前照灯(H4) | 47 | 排出ガス規制(モペッド) |
| 21 | 内部突起 | 48 | 灯火器の取り付け |
| 22 | モータサイクルおよびモペッドヘルメット | 49 | ディーゼルエンジン排出ガス規制 |
| 23 | リバースランプ | 50 | 灯火器(モペッド・モーターサイクル) |
| 24 | ディーゼル自動車排出ガス規制 | 51 | 騒音 |
| 25 | ヘッドレスト | 52 | 小型バスの構造 |
| 26 | 外部突起(乗用車) | 53 | 灯火器の取り付け(二輪車) |
| No. | 規則名 | No. | 規則名 |
|---|---|---|---|
| 54 | タイヤ(商用車) | 88 | 後方反射タイヤ(二輪車) |
| 55 | 車両用連結装置 | 89 | 速度制限装置 |
| 56 | 前照灯(モペッド) | 90 | 交換用ブレーキライニングアッセンブリおよびドラムブレーキライニング |
| 57 | 前照灯(二輪車) | 91 | サイドマーカーランプ |
| 58 | リヤアンダーランプロテクション | 92 | 交換用消音装置(二輪車) |
| 59 | 交換用消音装置 | 93 | フロントアンダーランプロテクション |
| 60 | コントロール類の表示(二輪車・モペッド) | 94 | 前面衝突時における乗員の保護 |
| 61 | 外部突起(商用車) | 95 | 側面衝突時における乗員の保護 |
| 62 | 不正防止装置(二輪車) | 97 | 車両警報システム |
| 63 | 騒音(モペッド) | 98 | ヘッドランプ(ガスディスチャージ式) |
| 64 | テンポラリーホイール/タイヤ、ランフラットタイヤ | 99 | ガスディスチャージ光源 |
| 65 | 特殊警告灯 | 100 | バッテリー式電気自動車 |
| 66 | スーパーストラクチャー強度(大型乗用車) | 101 | CO2エミッションと燃費(乗用車) |
| 67 | LPG車両の特定機器 | 102 | クロース型連結装置 |
| 68 | 最高速度測定法 | 103 | 交換用触媒コンバータ |
| 70 | 大型車後部表示板 | 104 | 大型車両用反射板 |
| 72 | ハロゲン前照灯(二輪車用HS1) | 105 | 危険物輸送車両構造 |
| 73 | 大型車側面保護 | 107 | 二階建てバスの構造 |
| 74 | 灯火器の取り付け(モペッド) | 108 | 更生タイヤ(乗用車) |
| 75 | タイヤ(二輪車・モペッド) | 109 | 更生タイヤ(商用車) |
| 76 | 前照灯(モペッド) | 110 | CNG 使用車 |
| 77 | パーキングランプ | 111 | 転覆安定性(カテゴリーNおよびOのタンク車) |
| 78 | ブレーキ(Lカテゴリー車) | 112 | 前照灯(非対称すれ違いビーム) |
| 79 | ステアリング装置 | 113 | 前照灯(対称すれ違いビーム) |
| 80 | シート(大型車) | 114 | 交換用エアバッグシステム |
| 81 | 後写鏡(二輪車) | 115 | LPG/CNG レトロフィットシステム |
| 82 | ハロゲン前照灯(モペッド用HS2) | 116 | 盗難防止装置 |
| 83 | エンジン燃料要件別の汚染物質 | 117 | タイヤ単体騒音規制 |
| 84 | 燃費測定法 | 118 | バスの室内艤装品難燃化 |
| 85 | 馬力測定法 | 119 | コーナリングランプ |
| 87 | データイムランニングランプ | 121 | 手動コントロール装置、テルテール、インジケーターの位置および識別 |
| No. | 規則名 | No. | 規則名 |
|---|---|---|---|
| 122 | 暖房システム | 137 | 拘束装置を中心 とした前面衝突 |
| 123 | AFS | 138 | 車両接近通報装置 |
| 124 | 乗用車用ホイール | 139 | ブレーキアシストシステム (BAS) |
| 125 | 前方視界 | 140 | 横滑り防止(ESC)システム |
| 126 | 仕切りシステム | 141 | タイヤ空気圧監視システム (TPMS) |
| 127 | 歩行者保護 | 142 | タイヤの取り付け |
| 128 | LED光源 | 143 | ヘビーデューティデュアルフューエルエンジンレトロフィットシステム(HDDF-ERS) |
| 129 | 改良型幼児拘束装置(ECRS) | 144 | 事故緊急通話システム(AECS) |
| 130 | 車線逸脱警報装置 (LDWS) | 145 | ISOFIXアンカレッジシステム、ISOFIXトップテザーアンカレッジおよびアイサイズ着席位置 |
| 131 | 衝突 被害軽減制動制御装置(AEBS) | 146 | 水素燃料二輪車の安全 |
| 132 | 改良型排出制御装置 (REC) | 147 | 農耕車両用カップリング |
| 133 | 自動車の再利用 | 148 | 動力駆動車両およびそのトレーラー用の光信号装置(ランプ) |
| 134 | 燃料電池自動車 (HFCV) | 149 | 道路照明装置(ランプ)・電動車両のシステム |
| 135 | ポール側面衝突 (PSI) | 150 | 電動車両とそのトレーラーの再帰反射装置とマーキング |
| 136 | カテゴリLの電気自動車 (EV-L) | 151 | 自転車検知のための死角情報システム |
2-1) 日本が受け入れている車載機器の規則概要と一覧
日本が現在(2019.12)、受け入れている規則を下記に記載する。
| No. | 規則名 | No. | 規則名 |
|---|---|---|---|
| 3 | 反射装置 | 60 | コントロール類の表示(二輪車・モペッド) |
| 4 | 後部番号灯 | 62 | 不正防止装置(二輪車) |
| 6 | 方向指示器 | 64 | テンポラリーホイール/タイヤ、ランフラットタイヤ |
| 7 | フロントおよびリアポジション(サイド)ランプ、ストップランプ およびエンドアウトラインマーカーランプ | 66 | スーパーストラクチャー強度(大型乗用車) |
| 10 | 電磁両立性に関する統一規定 | 70 | 大型車後部表示板 |
| 11 | ドアラッチ・ヒンジ | 75 | タイヤ(二輪車・モペッド) |
| 12 | ステアリング機構 | 77 | パーキングランプ |
| 13 | ブレーキ(カテゴリM、N、O車両) | 78 | ブレーキ(Lカテゴリー車) |
| 13-H | ブレーキ(M1) | 79 | ステアリング装置 |
| 14 | 安全ベルト(シートベルト)アンカレッジ | 80 | シート(大型車) |
| 16 | 安全ベルト(シートベルト) | 81 | 後写鏡(二輪車) |
| 17 | シート | 87 | データイムランニングランプ |
| 19 | 前部フォグランプ | 91 | サイドマーカーランプ |
| 21 | 内部突起 | 93 | フロントアンダーランプロテクション |
| 23 | リバースランプ | 94 | 前面衝突時における乗員の保護 |
| 25 | ヘッドレスト | 95 | 側面衝突時における乗員の保護 |
| 26 | 外部突起(乗用車) | 98 | ヘッドランプ(ガスディスチャージ式) |
| 27 | 三角警告板 | 99 | ガスディスチャージ光源 |
| 28 | 警音装置 | 100 | バッテリー式電気自動車 |
| 30 | タイヤ(乗用車) | 104 | 大型車両用反射板 |
| 34 | 車両火災の防止 | 110 | CNG 使用車 |
| 37 | フィラメントランプ | 112 | 前照灯(非対称すれ違いビーム) |
| 38 | リヤフォグランプ | 113 | 前照灯(対称すれ違いビーム) |
| 39 | スピードメーター | 116 | 盗難防止装置 |
| 41 | 騒音(二輪車) | 117 | タイヤ単体騒音規制 |
| 43 | 安全ガラス材料の認証に関する統一規定 | 119 | コーナリングランプ |
| 44 | 幼児拘束装置 | 121 | 手動コントロール装置、テルテール、インジケーターの位置および識別 |
| 45 | ヘッドランプ・クリーナ | 123 | AFS |
| 46 | 後写鏡 | 125 | 前方視界 |
| 48 | 灯火器の取り付け | 127 | 歩行者保護 |
| 50 | 灯火器(モペッド・モーターサイクル) | 128 | LED光源 |
| 51 | 騒音 | 129 | 改良型幼児拘束装置(ECRS) |
| 54 | タイヤ(商用車) | 130 | 車線逸脱警報装置 (LDWS) |
| 58 | リヤアンダーランプロテクション | 131 | 衝突 被害軽減制動制御装置(AEBS) |
| No. | 規則名 | No. | 規則名 |
|---|---|---|---|
| 134 | 燃料電池自動車 (HFCV) | 140 | 横滑り防止(ESC)システム |
| 135 | ポール側面衝突 (PSI) | 141 | タイヤ空気圧監視システム (TPMS) |
| 136 | カテゴリLの電気自動車 (EV-L) | 142 | タイヤの取り付け |
| 137 | 拘束装置を中心 とした前面衝突 | 144 | 事故緊急通話システム(AECS) |
| 138 | 車両接近通報装置 | 145 | ISOFIXアンカレッジシステム、ISOFIXトップテザーアンカレッジおよびアイサイズ着席位置 |
| 139 | ブレーキアシストシステム (BAS) | 146 | 水素燃料二輪車の安全 |
3) 車載機器の統一規定『ECE Regulation10(R10)』の紹介と一覧
ECE Regulation10(R10)は、EMC(電磁両立性)に関する統一規定であり多くの製品に対して要求がある。
Regulationの中には、認証を取得するために必要な様々な要件の記載があるが、今回はその中で試験要求について下記に記載する。
また、ECE Regulation10.05以降ではREESSに対する要求が追加されている。
こちらは、REESSのAC入力に対する要求が大きくは追加されている。また、Annex7~Annex9においてもREESSにおけるセットアップの違いなどが記載されている。
※REESS:車両の電気推進用に電気エネルギーを提供する充電式エネルギー貯蔵システム
ECE Regulation10.06の試験内容は下記一覧のとおりである。
| 項目 | 試験内容 | 規格 | REESS以外 | REESS |
|---|---|---|---|---|
| Annex 7 | 広帯域放射エミッション | CISPR25 | 〇 | 〇 |
| Annex 8 | 狭帯域放射エミッション | CISPR25 | 〇 | |
| Annex 9 | アンテナ照射イミュニティ | ISO11452-2 | 〇 | 〇 |
| TEMCELL イミュニティ | ISO11452-3 | 〇 | 〇 | |
| BCI イミュニティ | ISO11452-4 | 〇 | 〇 | |
| ストリップライン イミュニティ | ISO11452-5 | 〇 | 〇 | |
| Annex 10 | 伝導過渡エミッション | ISO7637-2 | 〇 | 〇 |
| 伝導過渡イミュニティ | ISO7637-2 | 〇 | 〇 | |
| Annex 17 | AC 電源線の高調波エミッション | IEC 61000-3-2 | 〇 | |
| Annex 18 | AC 電源線の電圧変化、電圧変動、フリッカエミッション | IEC 61000-3-3 | 〇 | |
| Annex 19 | AC/DC 電源線のRF伝導エミッション | CISPR 16-2-1 | 〇 | |
| CISPR 16-1-2 | 〇 | |||
| Annex 20 | 信号線のRF エミッション | CISPR 22 | 〇 | |
| Annex 21 | AC/DC 電源線へのEFTB イミュニティ | IEC 61000-4-4 | 〇 | |
| Annex 22 | AC/DC 電源線への雷サージイミュニティ | IEC 61000-4-5 | 〇 |
4) ECE Regulation10(R10)車載機器EMC試験の紹介と一覧
代表的な車載機器EMC試験の紹介としてECE Regulation10をベースに以下の項目を一覧で紹介する。
また、ECE Regulation10(R10)ではイミュニティ関連機能の有無により要求される試験項目が異なっている。
| 項目 | 試験内容 | 規格 | REESS以外 | REESS |
|---|---|---|---|---|
| Annex 7 | 広帯域放射エミッション | CISPR25 | 〇 | 〇 |
| Annex 8 | 狭帯域放射エミッション | CISPR25 | 〇 | |
| Annex 9 | アンテナ照射イミュニティ | ISO11452-2 | 〇 | 〇 |
| TEMCELL イミュニティ | ISO11452-3 | 〇 | 〇 | |
| BCI イミュニティ | ISO11452-4 | 〇 | 〇 | |
| ストリップライン イミュニティ | ISO11452-5 | 〇 | 〇 | |
| Annex 10 | 伝導過渡エミッション | ISO7637-2 | 〇 | 〇 |
| 伝導過渡イミュニティ | ISO7637-2 | 〇 | 〇 |
※イミュニティ関連機能
(a)車両の直接制御に関する機能:
- 劣化/変化:例) エンジン、ギヤ、ブレーキ、サスペンション、アクティブステアリング、速度制限装置;
- 運転者位置への影響:例) シートまたはステアリングの位置決め;
- 運転者の視認性への影響:例) ディップビーム、フロントガラスワイパー
(b)運転者、乗客その他道路利用者保護に関する機能:
- 例) エアバッグ及び安全拘束装置を含む。
(c)妨害時、運転者または他の道路利用者に混乱を引き起こす機能:
- 光の外乱:運転者の直視で観察されるかもしれない(a)または(b)の機能に関連する誤った操作。
例) 警告インジケータ、ランプまたはディスプレイからの間違った情報、警告、方向指示器、ストップランプ、エンド輪郭マーカランプ、後部位置ランプ - 音響外乱:例) 盗難防止警報、ホーン。
(d)車両データバス機能に関する機能:
- 他のイミュニティ関連機能の正しい機能を保証するために必要な、データの送信に使用される車両データバスシステム上のデータ送信をブロックすること。
(e)妨げられたときに車両の法定データに影響する機能。タコグラフ、走行距離計。
(f)電力網に結合されたときの充電モードに関連する機能:
- 車両テストの場合:予想外の車両運動につながる。
- ESA試験の場合:誤った充電条件(過電流、過電圧など)が発生する。
4-2) 車載機器EMC試験の紹介
4-2-1) ECE Regulation10(R10) Annex7/Annex8
ECE Regulation10(R10) Annex7/Annex8 では対象となる製品から照射される電磁エミッションについての規定となる。
まずは、測定方法として引用しているCISPR25について概要を記載する。
CISPR25は車両内で発生するノイズから車両搭載受信機を保護するために制定された規格であり、その目的のために以下の内容について規定しているでの一覧形式で記載する。
- - 車両の電気系統からの電磁エミッションの測定方法
- - 車両の電気系統からの電磁エミッションに対する許容値
- - 車両と無関係の車載部品の測定方法
- - 車載部品からの電磁エミッションの許容値
CISPR25において車載部品に対する測定は①放射エミッション、②伝導エミッション(電圧)、③伝導エミッション(電流)の3つがある。ECE Regulation10(R10)では①放射エミッションのみの要求であり、また周波数範囲も下記のように異なっている。
| ECE Regulation10.06 周波数範囲 | CISPR25 Ed4.0周波数範囲 |
| 30~1000MHz | 150KHz~2500MHz |
[ECE Regulation10(R10)広帯域放射エミッション/狭帯域放射エミッション 概要]
ECE Regulation10(R10)のAnnex7,8における放射エミッションはDUTから漏れ出ているノイズに関して測定を実施し、そのノイズレベルが許容値以下であるかを評価するものとなる。測定方法はCISPR25を引用しており、周波数範囲は30-1000MHzとなる。また、測定されたノイズに対して広帯域ノイズであるか、狭帯域ノイズであるかを判別して各々の許容値に対して評価が行われる。(*広帯域ノイズ/狭帯域ノイズの切り分け方法については下記に後述する。)
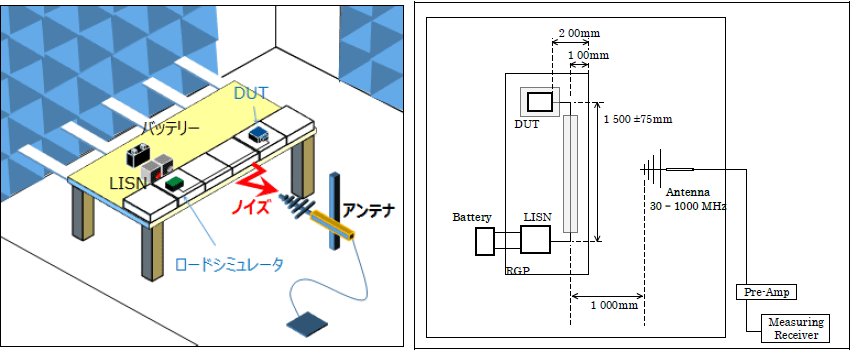
- [配置]
- -DUTは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネスは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネスはアンテナ側のグランドプレーンのエッジから100mm±10mmの距離に置く
- -ハーネスはグランドプレーン全面に1500±75mmで配置する。
- -DUTとロードシミュレータ間のハーネスは2000mmを超えない。
- [測定機器]
- -アンテナ-ハーネス間距離を1000mm±10mmにする。
- -アンテナの高さはグラウンドプレーン上100mm±10mmにする。
上記セットアップにて、30~1000MHzのノイズを測定を実施する。この時出ているノイズに対して下記のような切り分けを行い評価を行う。
広帯域エミッション/狭帯域エミッションノイズの切り分け方法 (CISPR25 2nd)
- 測定されたノイズに対してテストレシーバを使用して尖頭値検波[XPK(dBuV/m)]、平均値検波[XAV(dBuV/m)]で測定を実施する。
- この時測定された値を尖頭値検波 測定結果:XPK(dBuV/m)、平均値検波 測定結果:XAV(dBuV/m)とすれば広帯域、狭帯域は以下のように切り分けられる。
XPK - XAV が6dB以下である場合:狭帯域ノイズ
XPK - XAV が6dBを超える場合 :広帯域ノイズ
XPK - XAV が6dBを超える場合 :広帯域ノイズ - ECE Regulation10では狭帯域ノイズは平均値検波、広帯域ノイズは準尖頭値検波となるため、そちらの測定結果と許容値を比較して評価を行う。
4-2-2) RFイミュニティ対する要求
イミュニティ関連機能がある場合、ECE Regulaion10ではイミュニティ関連機能に対してRFイミュニティを実施し耐性を評価する必要がある。
- その場合、ECE Regulaion10.06で要求される周波数は下記となる。
- 周波数:20~2000MHz
- 変調:AM変調 [1kHz,80%] (20~800MHz)、PM変調 [577μs ON,4600μs Period] (800~2000MHz)
また、その車載機器のEMC試験方法については以下の4つの中から選択することができ、また複数の方法を選ぶこともできる。いずれの方法を用いたとしても上記に規定された周波数を満たすことができれば良い。
| No. | 規格タイトル | 規格番号 | ECE Regulation10.6 試験レベル |
|---|---|---|---|
| 1 | 吸収材に裏打ちされたシールドルーム | ISO11452-2 | 30V/m |
| 2 | トランスバース電磁モード(TEM)セル | ISO11452-3 | 75V/m |
| 3 | ハーネス励磁法 | ISO11452-4 | 60mA |
| 4 | ストリップライン | ISO11452-5 | 60V |
[ECE Regulation10 Annex9 ALSE法(ISO11452-2) 概要]
ECE Regulation10 Annex9では前述のように方法を4つから選択することができる。
ALSE法(ISO11452-2)は、その内の一つでありALSE内部でアンテナを用いて電波としてノイズを印加する方法となる。また、ALSE法によるアンテナ照射の方法である場合低周波のノイズを照射することが困難であり一般的には200MHz以降の周波数帯で多く用いられる手法となる。
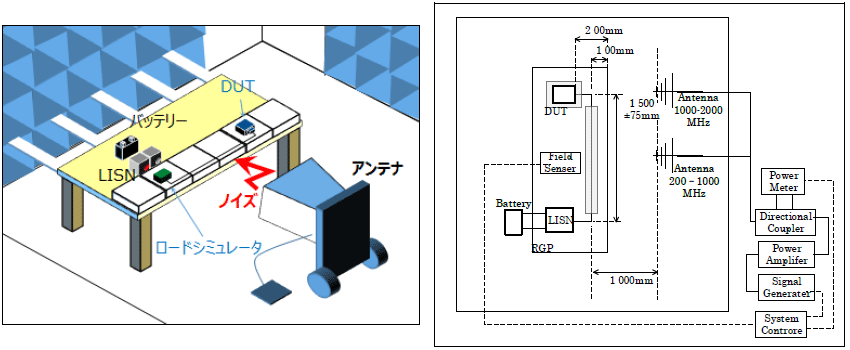
- [配置]
- -DUTは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネスは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネスはアンテナ側のグランドプレーンのエッジから100mm±10mmの距離に置く
- -ハーネスはグランドプレーン全面に1500±75mmで配置する。
- -DUTとロードシミュレータ間のハーネスは2000mmを超えない。
- [測定機器]
- -アンテナ-ハーネス間距離を1000mm±10mmにする。
- -アンテナの高さはグラウンドプレーン上100mm±10mmにする。
- -アンテナの水平方向の位置は以下にする。
200-1000MHz ハーネス中央前
1000-2000MHz DUT正面
ALSE法の試験は置換法を用いて試験を行う。
置換法とは対象製品、ロードシミュレータ、LISN、Batteryなどが無い状態で試験レベルとなるように値付けを行いその条件を利用して、実際の試験を行う。以下に置換法の概要を記載する。
- 試験系(アンテナ-アンプ-信号発生器)などは試験実施時と同じものを使用する。
- 各周波数帯で基準位置となる場所に電界センサーを配置する。
- 電界センサーで試験レベルになるように、信号発生器を調整し記録する。
- 3で得られた信号発生器のレベルを試験にて設定し試験を実施する。
[ECE Regulation10 Annex9 TEMセル法(ISO11452-3) 概要]
ECE Regulation10 Annex9では前述のように方法を4つから選択することができる。
TEMセル法(ISO11452-3)は、その内の一つでありTEMセル内部で電波としてノイズを発生させ、TEMセル内部に配置した電子機器へノイズを暴露する方法となる。また、TEMセル法である場合高周波のノイズを照射することが困難であり一般的には200MHz以下の周波数帯で多く用いられる手法となる。
また、TEMセルはセル内部に製品を配置するためTEMセルの物理的寸法によって製品サイズの大きなものの試験には適さないものとなる。
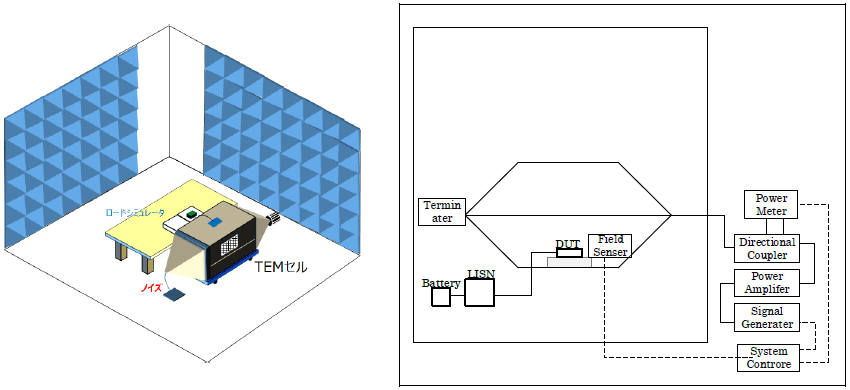
- [配置]
- -絶縁支持台はTEMセルの高さの6分の1にする。
- -DUTは絶縁支持台の中央に配置する。
- 配置については、DUTのみの場合とDUT及びハーネスを暴露する場合がある。
- -DUTのみの場合は電源線及び信号線はTEMセルの床に固定し、TEMセル壁のコネクタからDUTの間をシールドします。
- -DUT及びハーネスを暴露する場合はTEMセル壁面のコネクタからの電源線及び信号線をDUTに直結する。
TEMセル法の試験はALSE法と同様に置換法を用いることもできるが、TEMセル法は以下の計算式を用いた方法でも試験することができる。
1. 試験時に電力を測定し、下記式を用いて電界を計算して試験を実施する。
- E = (Z*Pnet)^0.5/d
- E:電界強度 [V/m] 試験レベル
- Z:TEMセルの特性インピーダンス
- Pnet:正味電力
- D:床からTEMセル内のセプタムまでの距離
[ECE Regulation10 Annex9 BCI法(ISO11452-4) 概要]
ECE Regulation10 Annex9では前述のように方法を4つから選択することができる。
BCI法(ISO11452-2)は、その内の一つでありインジェクションプローブを用いて対象製品のハーネスにノイズを重畳させる方法となる。
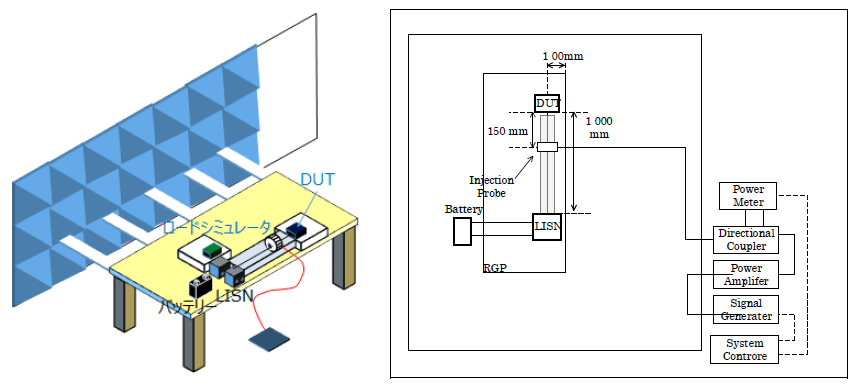
- [配置]
- -DUTは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネスは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネス長は1700mm(置換法)、1000mm(閉ループ法)にする。
- [測定機器]
- -注入プローブは以下の位置に配置する。
置換法:DUTから150mm、450mm、750mm位置
閉ループ法:DUTから900mm位置 - -電流プローブは以下の位置に配置する。
置換法:DUTから50mm位置 (任意)
閉ループ法:DUTから50mm位置
BCI法の試験はALSE/TEMセル法と同様に置換法を用いることもできるが、閉ループ法を用いてEMC試験をすることができる。
[閉ループ法]
- 注入プローブ、電流プローブを上記記載の位置に配置し、DUTなどのセットアップ、動作は試験状態とする。
- 注入プローブに電力を注入し、電流プローブにて電流(ノイズレベル)を測定する。
- 測定された電流が下記に達するまで注入プローブへの電力を上げる。
- 測定された電流が試験レベルに到達する。
- 試験レベルが校正時の進行波電力が4倍に達する。 - 3.の条件に達した状態で製品にノイズを印加して評価を行う。
4-2-3) 過渡エミッション/過渡イミュニティの判定基準
ECE Regulation10 Annex10で要求される過渡エミッション、過渡イミュニティは製品の電源に対する評価となる。
また、過渡イミュニティ試験に関して前述のイミュニティ関連機能の有無により合否判定基準が異なる。
過渡イミュニティ試験の合否判定基準について下記に記載する。
| 試験パルス | 試験レベル | イミュニティ関連機能 | |
|---|---|---|---|
| 関連する | 関連しない | ||
| Pulse 1 | Ⅲ | C | D |
| Pulse 2a | Ⅲ | B | D |
| Pulse 2b | Ⅲ | C | D |
| Pulse 3a/3b | Ⅲ | A | D |
| Pulse 4 | Ⅲ | B
(エンジン始動の段階で作動しなければならないESAの場合) C
(その他のESAの場合)
|
D |
クラスA:装置/システムのすべての機能は、妨害にさらされている間及びその後に、設計されたとおりに機能する。
クラスB:装置/システムのすべての機能は、妨害にさらされている間は、設計されたとおりに機能する。しかしながら、それらの機能のうちの一つ又は複数が、規定の許容誤差を超えることがある。すべての機能は、妨害にさらされることがなくなれば、自動的に通常の限度値い内に戻る。メモリ機能は、クラスAのままとする。
クラスC:装置/システムの一つ又は複数の機能が、妨害にさらされている間は設計されたとおりに機能せず、妨害にさらされることがなくなれば、自動的に通常の動作に戻る。
クラスD:装置/システムの一つ又は複数の機能が、妨害にさらされている間は設計されたとおりに機能せず、妨害にさらされることがなくなって、かつ、装置システムが簡単な"操作者/使用"の動作でリセットされるまで、通常の動作に戻らない。
[ECE Regulation10 Annex10 過渡エミッション 概要]
ECE Regulation10 Annex10で要求される過渡エミッションは、対象製品の電源に対してON⇒OFF、OFF⇒ON時に発生する過渡現象をオシロスコープで測定し、評価するものとなる。
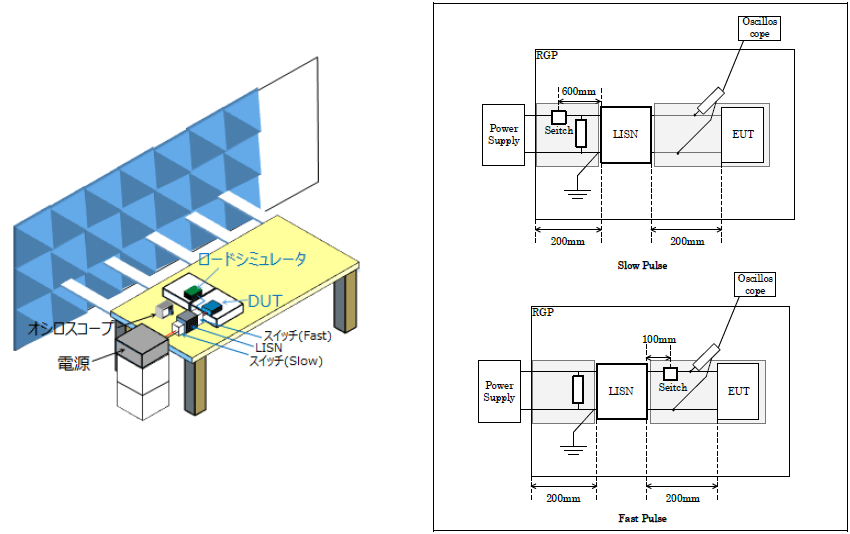
- [配置]
- -DUTは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネスは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネス長は1700mm(置換法)、1000mm(閉ループ法)にする。
- [測定機器]
- -Slow測定時にSWをLISNから600mm位置に配置する。
- -Fast測定時にSWをLISNから100mm位置に配置する。
[ECE Regulation10 Annex10 過渡イミュニティ 概要]
ECE Regulation10 Annex10で要求される過渡イミュニティは、対象製品の電源に対して車両内で発生すると考えられる過渡パルス、電源変動を模擬した状態を作り、その耐性を確認する試験となる。
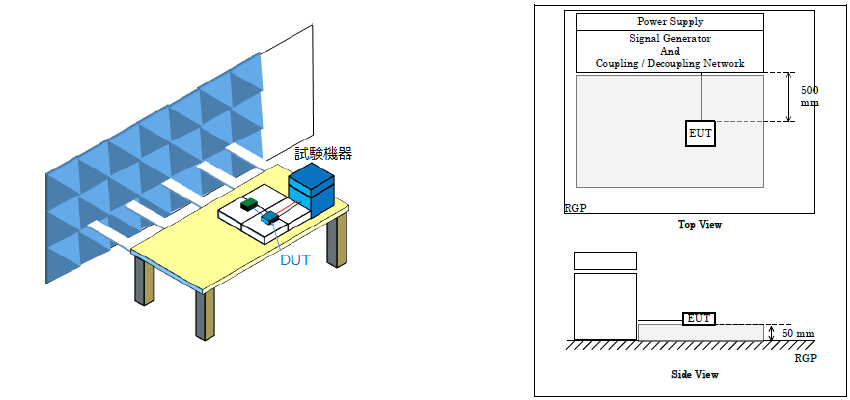
- [配置]
- -DUTは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネスは50±5mmの絶縁材(ε <1.4)の上に配置する。
- -ハーネス長は500mm(パルス3のみ)にする。
印加する過渡パルス、電源変動について下記にそれらが何を模擬しているのかを記載する。
-Pulse1:誘導性負荷から電源を遮断することによって発生する過渡現象の模擬。
-Pulse2a:ワイヤーハーネスのインダクタンスによる、DUTと並列に接続された装置における電流の突発性遮断によって発生する過渡現象の模擬
-Pulse2b:点火スイッチが切られた後に、発電機として動作する直流モータから発生する過渡現象の模擬
-Pulse3a/3b:スイッチの開閉プロセスの結果として発生する過渡現象の模擬
-Pulse4:始動に伴うスパイクを除き、内燃機関のスタータモータ回路に通電することによって発生する電圧の低減の模擬
(著)日本品質保証機構


